「民泊を始めてみたいけど、許可申請の流れが分からない…」
「自分で許可申請をできるか不安…」
初期投資が少なく、空き家を有効活用できる民泊に注目が集まっています。さらに、訪日外国人が増えている状況が後押しして、民泊運営を始める方も増えています。
しかし、必要な許可を取らずに無許可で民泊運営を行うと法律で罰せられます。
この記事では、民泊の許可を得る方法や許可申請の流れ、許可を得た後にやるべきことを詳しく解説しています。
許可申請をスムーズに終わらせる方法まで紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
民泊とは

民泊とは、個人の住宅や空き部屋を旅行者に有償で貸し出す宿泊サービスです。
観光庁の発表によると、2023年12月〜2024年1月までの2か月間で、全国の民泊宿泊日数は前年同期比27.7%増の23万9,333人となりました。また、2024年3月15日時点の民泊届出住宅数は2万3,142件で、前年同月から23%増加しています。
出典:民泊制度ポータルサイト‐国土交通省
今後訪日外国人の増加とともに、民泊の需要はますます高まっていくでしょう。
民泊の許可を得る方法は3種類

民泊運営に関する許可は大きく分けて3種類です。
それぞれ異なる法的要件と自治体の規則を持っており、物件に合わせて適切な手続きを踏む必要があります。
- 旅館業法の簡易宿所営業
- 特区民泊における民泊経営
- 民泊新法が定める民泊経営
それぞれ解説します。
旅館業法の簡易宿所営業
旅館業法とは、旅館業の適正な運営と健全な発達を確保し、利用者のニーズに対応したサービス提供の促進を目的とした法律です。民泊の許可を得る方法で最も一般的なのが、旅館業法の簡易宿所として許可を得る方法です。
旅館業法の簡易宿所として許可を得る最大のメリットは、180日間の営業日数制限がないことです。後述する民泊新法では1年間で営業できる日数が決められており、定めた日数を超えての運営はできません。
その点、旅館業法では営業日数の縛りがないため売上を最大化することができます。
デメリットは、他の方法と比較して申請の難易度が高いことです。非常用照明や消防設備などの設置が必要となるため、初期投資コストにも注意が必要です。
民泊新法が定める民泊経営
民泊新法(正式名称は住宅宿泊事業法)は、急速に増加する民泊について、安全面・衛生面の確保や近隣トラブルの防止を目的として、2018年6月に制定された法律です。他の方法と比較して申請のハードルが低く、注目を集めています。
民泊新法のメリットは、旅館営業が認められていない住居専用地域での営業が可能な点が挙げられます。旅館業法に比べ、開業可能なエリアが大きく増えるため、物件の選択肢も広がるでしょう。また、旅館業法ほど消防設備等の基準が厳しくなく、初期費用を抑えられる点もメリットです。
民泊新法最大のデメリットは、営業日数に制限があることです。年間180日までしか営業できないため、収益性は下がります。また、居室数が6室以上ある、または家主不在型民泊に該当する場合は、住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要がある点にも注意が必要です。
特区民泊における民泊経営
特区民泊は、地域振興と国際競争力の向上を図るために指定されている国家戦略特別区域(略して特区)内で営業できる民泊形態です。特区内は旅館業法の規定対象外となり、特区民泊独自の認定制度が適用されます。
特区民泊のメリットは、申請が通りやすいとこにあります。旅館業法では、消火器や誘導灯、スプリンクラーなどの消防設備を揃えなければ営業の許可が下りません。一方、特区民泊は消防設備の基準が緩和されているため、一般的な物件でも審査が通りやすい特徴があります。
また、営業可能日数に制限がないことも特徴の一つと言えます。
デメリットとしては、最低宿泊日数に制限があることが挙げられます。宿泊客は最低2泊3日以上の滞在が必要で、短期滞在のビジネス客などを受け入れられません。また特区内には民泊が集中しているため、価格競争に巻き込まれやすい点もデメリットといえるでしょう。
現在特区民泊が許可されているのは、大田区、大阪府、福岡市、北九州市、新潟市、千葉市などです。(2025年1月時点)
民泊許可申請の流れ
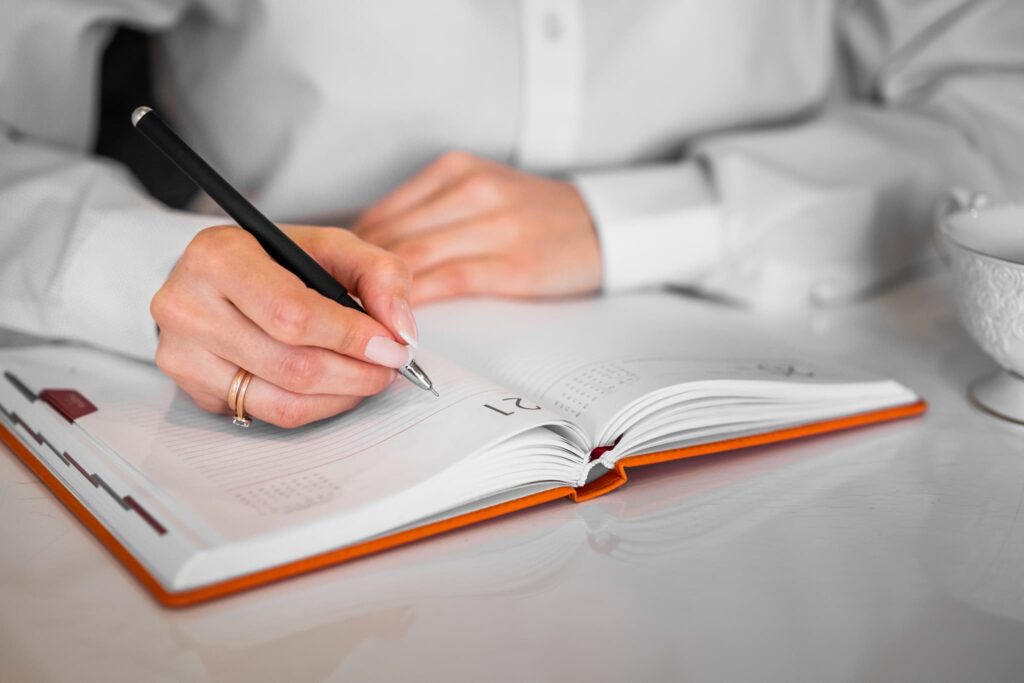
民泊許可申請の一般的な流れは以下のとおりです。
- 自治体の相談窓口へ事前確認
- 必要書類の提出
- 設備に関する適合検査
- 予約サイトへの登録
それぞれ解説します。
自治体の相談窓口に事前確認
民泊の許可申請を行うためには、保健所に必要書類を提出する必要があります。しかし、最初から保健所には行かずに、自治体の相談窓口に行くことが重要です。
自治体の相談窓口に行くと、施設の所在地や図面、建築基準法や消防法への適合状況、マンション管理規約などの確認ができます。また自治体によって異なる必要書類や規則等も教えてもらえるため、手続きをスムーズに進められるでしょう。
必要書類の提出
準備ができたら保健所に必要書類を提出します。一般的な必要書類は以下の通りです。
- 履歴事項全部証明書
- 敷地配置図
- 求積図
- 建物立面図(四方向)
- 寸法入り平面図
- 土地、建物登記簿
- 消防法令適合通知書(後述)
- 使用承諾書(必要に応じて)
- 水質検査成績書(必要に応じて)
必要書類は自治体によって異なるため、詳細は必ず自治体の相談窓口で確認してください。
「消防法令適合通知書」の取得方法
「消防法令適合通知書」は、宿泊施設が消防法令に従った設備を備えていることを確認するための書類です。各自治体の消防署から発行されます。
申請の流れは以下の通りです。
- 事前相談: 所轄の消防署に相談し、必要な消防用設備等を確認します
- 設備の整備: 消防署の指導に従い、不足している消防設備を設置します
- 交付申請: 消防法令適合通知書交付申請書と必要書類(後述)を提出します
- 立入検査: 必要な場合は消防署による現地検査が行われ、設備が適正であるか確認されます
- 交付決定: 問題がなければ、消防法令適合通知書が交付されます
消防法令適合通知書の交付に必要な書類は以下の通りです。
- 消防法令適合通知書交付申請書
- 案内図(付近見取図)
- 立面図、各階平面図、設備配置図などの物件に関する図面
- 工事整備対象設備等着工届出書(必要に応じて)
- 消防用設備等設置届出書(必要に応じて)
- 防火対象物使用開始届出書(必要に応じて)
消防法令適合通知書は、申請してから取得まで1週間程度要します。早く民泊運営をスタートさせたいなら、消防関連の許可や申請手続きを先に進めておきましょう。
設備に関する適合検査
民泊の設備が所定の要件を満たしているか確認するために、設備に関する適合検査を受ける必要があります。
保健所の職員が施設を訪問し、設備の基準が満たされているか確認します。基準を満たしていなければ、許可を取得することはできません。
自治体独自の条例が定められていることもあるため、あらかじめ検査項目を確認しておくことがポイントです。
予約サイトへの登録
必要な許可を取得したら、予約サイトへ登録しましょう。
民泊経営において集客は最も重要な要素のひとつです。どれほど魅力的な施設であったとしても、旅行客に認知してもらえなければ宿泊してもらえません。
AirbnbやBooking.comなどの規模が大きな予約サイトに登録して、効果的に集客をしていきましょう。
民泊の許可を得た後にやるべきこと

新法で運営をスタートした場合、民泊事業者には「定期報告義務」が定められています。
報告内容は以下のとおりです。
- 届出住宅に人を宿泊させた日数
- 宿泊者数
- 延べ宿泊者数
- 国籍別の宿泊者数の内訳
報告期限は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日までとしており、直近2ヶ月分の報告を行う必要があります。
宿泊実績がない場合でも、その旨報告しなければなりません。報告を怠ったり虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金が課される可能性があるため、報告を怠らないようにしましょう。
※旅館業法では報告義務は課されていません。
民泊の許可申請は行政書士が代行可能

民泊の許可申請は行政書士が代行してくれます。
民泊の許可申請手続きは煩雑で時間がかかりますが、行政書士に依頼することで、時間と労力を大幅に節約できます。また、専門的な知識が豊富なのでスムーズな申請が可能です。
代行費用の相場は15〜40万円程度で、行政書士や許可申請の種類、施設の規模によっても異なります。
行政書士の資格を持っていない人は、民泊の許可申請に必要な書類を作成できません。事業者本人以外が許可申請を代行した場合、行政書士法違反となります。申請の代行を依頼する際は行政書士の資格を有しているか確認するようにしましょう。
民泊の許可申請は行政書士への依頼がおすすめ

この記事では、民泊の許可を得る方法や許可申請の流れ、許可を得た後にやるべきことを解説してきました。
民泊の許可申請手続きを行う際には、民泊に関する法律や規制を正確に理解し遵守する必要があります。行政手続きに慣れていない方にとっては、記入事項の多い申請書類の作成が大きな負担になることもあるでしょう。
民泊の許可申請を自分で行うことが難しい場合や、時間を節約したい場合は、行政書士への代行依頼がおすすめです。専門的な知識で民泊運営のスタートを力強くサポートしてくれるはずです。
Tabiiiでは、行政書士の紹介もサポートしています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

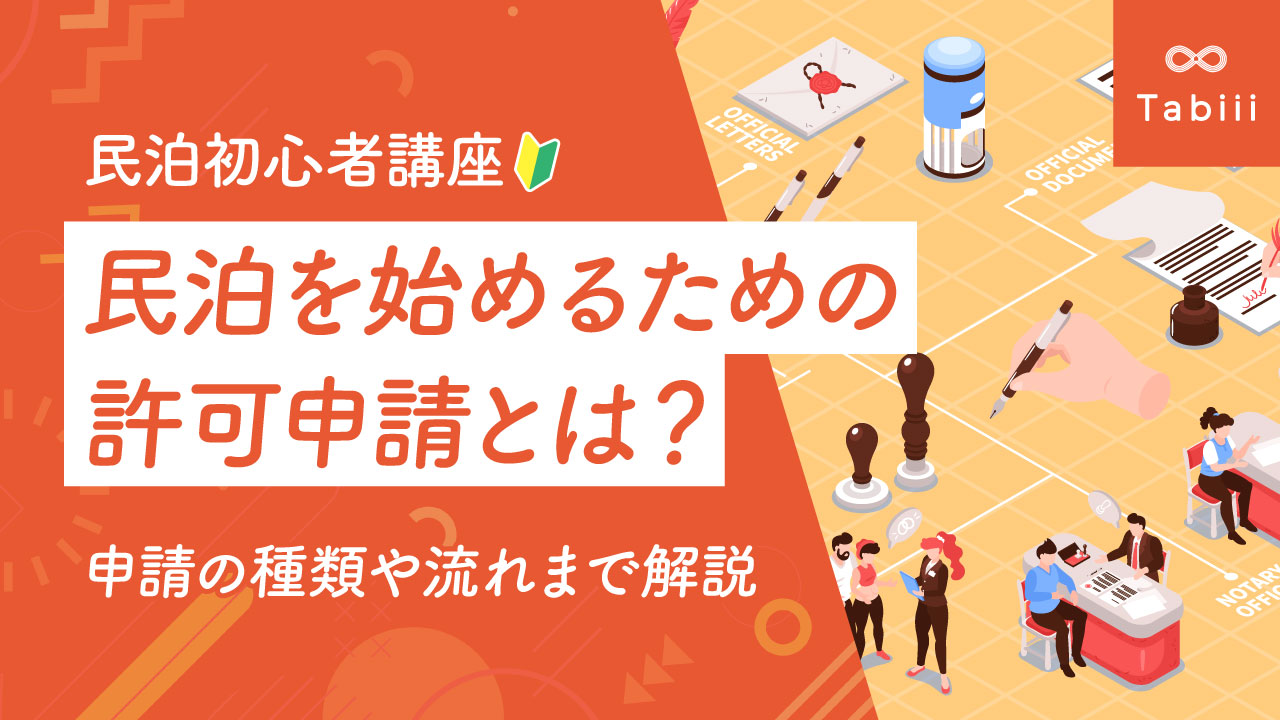

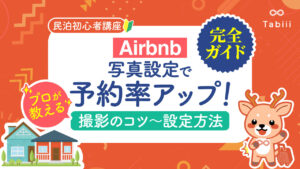
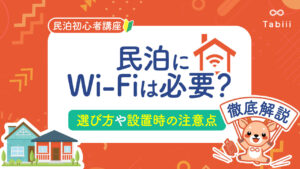
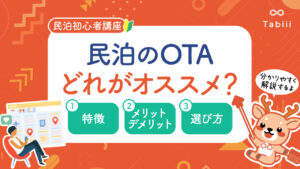

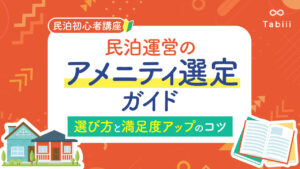

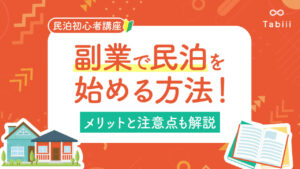
コメント
コメント一覧 (2件)
相談したい。
この度は記事へのコメントありがとうございます。
ご相談については、ホームページの問い合わせフォームからご連絡いただけましたら幸いです。
https://tabiii.co.jp/#contact
何卒よろしくお願いいたします。